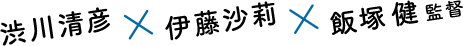何かを「辞める」人たちを描きたかった
渋川さんと飯塚監督は同じ群馬県渋川市のご出身だそうですね。
渋川清彦(以下、渋川):そうですね。だから俺はずっと意識してましたよ、同じ高校の卒業生だし。
飯塚健(以下、飯塚):しかも小学校まで一緒ですから。
伊藤沙莉(以下、伊藤):えぇ!?
渋川:そう。会ったのはこの映画が初めてだったけど、俺は渋川の町が好きだし、同郷の監督と地元で映画を撮れるなんて最初で最後だと思ったから、思い入れはものすごくありました。自分が生まれ育った場所で毎朝起きて、撮影現場まで向かうというのは、不思議な気持ちでしたよ。仕事してるのか遊んでるのか、何やってんだろうって(笑)。
今回は飯塚監督が自ら脚本を書いた完全なオリジナル作品ですが、なぜ、今、このドラマを撮ろうと思ったのでしょうか?
飯塚:プロデューサーの狩野善則さんから、渋川さんと僕とで、群馬を舞台にした映画を撮らないかと声をかけてもらったのが始まりです。決まっていたのはそれだけで、あとは自由にやっていい感じでしたので、逆に何を書こうか悩みましたが、僕の中で一つのテーマだった「辞める」ことを描いてみようと思って。
「辞める」というと?
飯塚:人生は何かを始めては辞めることの繰り返しだと思ってるので、次の一歩を踏み出すために現状を「辞める」話にしようかなと。誰にでもこうなりたい、こうしたいという希望があると思うんですけど、それを叶えるためには現状の何かを辞めなければいけないはずなんですよね。僕らの仕事でも、同じ時期に二つのオファーをいただいたら、どちらかを辞めなければいけない。それをもっと身近な形でドラマにできないかなと思ったんです。
渋川:「辞める」ということは、今の自分の生活ともリンクするものがあるなっていうのは、思いました。今やっていることを辞めてまた違うところに行くのか、いやでも簡単には辞めらんねえなっていうね。いわゆる世間一般が思う四十代っていう俺の年齢が、ちょうど人生の折り返し地点というか。ここから先どうするかっていうのは、個人的にもいろいろ思うことはあるので、そこは演じた榎田洋二郎とも重なりますね。
飯塚:脚本を書くときに、キーさん(渋川)ぽいんだけどキーさんぽくないところというのを意識していたので、榎田洋二郎はこれまでのキーさんのイメージがありつつ、わりと見たことのないキーさんの姿になっているんじゃないかと思うんですよね。
今までにない姿を見せたい
伊藤さんは飯塚組にとっては常連といってもいいぐらいですね。
伊藤:飯塚監督とはこれが六本目で、もちろんすごく信頼はあるんですけど、回を重ねれば重ねるほど、逆に怖いんですよ。どこかで見限られるんじゃないかっていう緊張感があるし、常に新しいものを見せて、やっぱりよかったなと思っていただきたいので。
飯塚:今回演じてもらった千秋は二十八歳の主婦だったけど、そんな年齢の役もまだやったことなかったんじゃない?
伊藤:そうですね。千秋はそれまで自分が演じた役の中で最年長だったんです。結婚している設定も初めてでした。
飯塚:年齢的にちょっと無理があるかなとか思ったりしながらも、だからこそ面白いんじゃないかという気がして。今まで一緒に生み出したキャラクターをまたなぞるのはイヤだしカッコ悪いから、過去にやってないアプローチでできたらいいなとは思ってました。
伊藤:女性としての経験みたいなところで言うと、結婚とか子供というのは私がまだ知らない世界なんですけど、結婚して子供がいる姉の話を聞いているときに千秋の言葉をふと思い出して無意識に言っちゃったりしてるんです。千秋って人の痛みに寄り添えるというか、相手の気持ちがわかる人だと思うんですよ。この映画に出てくる人たちはみんな痛みを知っている人たちだと思うんですけど、そういう意味で、私は千秋みたいな女性が好きだなと思います。
渋川:伊藤さんはね、体は小さいけど積んでいるエンジンみたいなものがデカいから。すごい上手いから、本当にやりやすいですよ。
伊藤:でも撮影中は監督から毎回「それいつもの沙莉が出てる」と言われてたんですよ。やっぱりどうしてもふざけたくなっちゃって(笑)。私がこの映画で唯一本当にふざけられたのは部屋に入って行く瞬間だけなんですよ。鍵をもらって、ドアが閉まる寸前で笑うところが、一番解放された瞬間だったと思います。一番ヘンな顔ができたシーンはあそこでしたね!
初めて地元にカメラを向けてもいいと思えた
榎田貿易堂の建物はこの映画のために作られたものですか?
渋川:あれはもともとあったところで。あの道を俺はよく通ってて、何なんだろうここはっていつも思ってたんですけど、おそらく館長が趣味で集めたものを日曜日だけ展示してるプライベートの美術館みたいな感じの場所なんですよ。
飯塚:僕は知らなかったんですけど、脚本を読んだKEE(渋川清彦)さんが、あそこのために書かれたような話だよねって。それで一緒に行ってみて。あの場所の説得力は大きかったですね。
名物の女性館長さんがいる珍宝館でのシーンも相当インパクトがありました!
伊藤:珍宝館でのシーンは、普段ああいったことをする機会はないので、楽しかったです……(笑)。
渋川:ああ、あそこか!
伊藤:ああいった場所でね、ああいったことを……衝撃的でしたよ! アプローチの仕方がわからなすぎてどうしようかと。ひたすら練習するといっても、大々的に練習するのもどうかっていう動きでしたし……もうがむしゃらでしたね。
飯塚:そこはもう、見てもらうしかないですね(笑)。僕はこの仕事で立派に食えるようになるまでは、ダサくて地元に帰れないっていう思いが常にあったんですよ。だから今回が初めてですよ、自分の生まれ育った町にカメラを向けたのは。地元でロケをしてもいいなっていう気持ちになれたのは大きかったです。
飲み会に台本を持ってくる榎田チーム
あらためて群馬での日々をふり返ると、皆さんにとってこの撮影はどんな経験になりましたか?
伊藤:私にとっては贅沢な時間でした。すごい先輩たちが並んでいる中に自分が入るのはもちろん緊張したし、毎回吐きそうでしたけど、絶対に吸収できるものもたくさんあるから、足を引っ張らないようにしなきゃなと思いつつ、嬉しい気持ちは大きかったです。渋川さんは思っていた以上に人間らしい方でしたし。
渋川:え、どういうこと!?
伊藤:榎田貿易堂に集まってくる人たちのことをちゃんとわかってくれている気がしたんです。撮影中は(森岡)龍さんとかも一緒にほぼ毎日ぐらいで飲みに行ってたんですけど、渋川さんも龍さんも「余裕」な感じじゃないというか。今日の撮影ではこういうところがあったよね、明日のここどうしようか、という会話が自然と始まるんです。
渋川:ああ、それなんかあった気がする(笑)。珍しいよね。
伊藤:何の話し合いもしてないのに、みんな台本を持って来るんですよ、飲み会に!
渋川:そうだっけ?
伊藤:持って来てました。それで、明日撮るこのシーンをちょっと準備しておこう、みたいな時間が必ずあって。自分も不安だったけど、私からは言い出しづらいことを、先輩の方が率先してやってくださったのでとても心強かったんですよ。
渋川:不安だったんだよね、みんな。上の人も不安なんだよ。
飯塚:オリジナル脚本だったというのもあるし、信頼のおける役者さんたちばかりだったので、現場で生まれるセッションのほうを大切にしました。信頼しているからこその「ゆとり」なのかもしれないですね。
まさにチームワークですね。この映画は現状を辞めるまでの話でしたが、続編への思いはいかがですか?
渋川:それはありますよ。
伊藤:うん。
渋川:一本ずつ主役がどんどん回っていっても面白い気はするんだよね。今回はこの人がメインというのが持ち回りになっていく。そこに新しい人もいっぱい入れていけるでしょ?
飯塚:そうですね。やるからには変な脚本を書きますよ、もちろん!